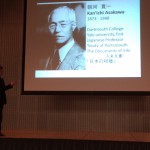農業改革はTTPとは関係なく日本の大きな課題です。なにしろ、日本農業の価値、可能性はとても高いのですから。
にもかかわらず、農業産物の輸出で稼ぐ力は、アメリカ、オランダ、ドイツ、ブラジル、フランスの順で、日本はなんと世界で「45位」あたりですから、何かおかしいと思いませんか?良いものに価値をつけて、世界に売ることができない日本の弱さの代表例です。
小泉進次郎さんの頑張りで進み始めてはいますが、最近でも農協(JA)の抵抗や、自民党の大きな票田ということで、一時的にせよ腰砕けになるとか、いろいろです。
内閣府の担当からこの問題について意見を聞かせてほしいというので、2日間にわたってヒアリングに参加しました。
農業の現場の方たちは皆さんがんばっているのですが、農家の時給は450~500円程度なのが結構多いようです。これはちょっとひどい状況ですね。
ヒアリングの2日目は、Oisixの高島さんと、Seak・「ゆる野菜」の栗田くんといった農業出身ではない方たちの農業事業のヒアリング。「ゆる野菜」モデルは、創業まだ2年半ほどですが、参加の農家の時給は、すでに2,000円近くになっていて、3年目には2,500円ほどを目標にしているそうです。
日本の農業という素晴らしいアセットを生かそうと頑張っている方たちです。
陪席した役所の方たちにも、この2人のプレゼンはインパクトがあったようでした。高島さんは以前から知っており、上場まで果たしている起業家です。栗田くんは私が連れて行きました。
栗田くんはWHILLの経営にかかわっていた頃に知りあったのですが、最近この農業の新しいモデル事業を始めたのです。素敵なビジネスモデルです。
このような若者たちが、停滞する日本を変える力です。みんなで応援しましょう。